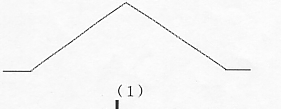 |
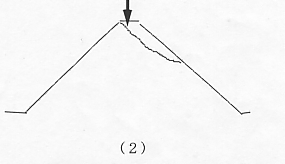 |
【テールアルメ崩壊原因に関する不整形段差の取り扱いについて】
1、論述の主旨
本件テールアルメ崩壊事故原因として争われた要因の一つに、テールアルメ壁体に見られた「不整形段差」というものがある。これは当初被控訴人Bから主張されたもので、テールアルメ壁体の一部にみられたコンクリートスキンの表面上のズレを、テールアルメ自体の強度低下に結びつけ、これを本崩壊事故原因の一つとし、更にその原因を控訴人Aの施工不良によるとするものである。この主張はA・C・D連名による「補強土(テールアルメ)壁工法調査報告書」(甲第20号証)、及び平成11年5月31日被控訴人D高見証言で明らかに否定されている。
しかしながら、被控訴人Bは、なお納得せず「平成12年10月31日付け準備書面で同主旨の主張を行っている(同6~7頁)。
又、一審判決ではテールアルメ崩壊原因について
「・・・・1)(不整形段差)、ないし2)(砕石置き換えの不備)のような本件テールアルメ壁の強度低下原因の存在により本件テールアルメ壁が崩壊したものと認めるのが相当である。・・・」(p72)とし、この結果控訴人の一部敗訴となったものである。
当鑑定人は、控訴人代理人より訴訟資料を受け取って以来、各種資料を慎重吟味してきたが、本判決文については「テールアルメ壁の強度低下原因の存在により」という言葉の意味が理解出来なかった。そのため本鑑定書作成ではこの点の検討を省略した。その理由は、そもそもテールアルメ壁には固有の強度というものが存在しないからである。存在しないものが低下するわけはないので言葉の意味が理解できない。理解出来ないものに対し反論も出来ない。従って、「無視」という手段を採らざるを得なかったのである。
又、テールアルメはそもそも、可撓性構造物であるということから、数㎝程度のスキンプレートのズレが全体の安定性にとって何ら関係は無いということを本鑑定で示せば、この問題は自ずから解決するという判断により、敢えてこの問題の詳述を避けたのである(理由は頁と時間の無駄を省くため)。
しかし、その後根本的な問題として、被控訴人もその代理人も、更に一審裁判官も「強度」という物理概念を十分に理解し得ていなかったことが、このような結論に至ったものと考えられるようになった。この点は鑑定人の説明不足もあるので、ここで改めて「不整形段差」というものが如何に意味のないものかを論述する事にする。
2、「強度」の概念について
結論からいうと、大学の土木工学科の試験やレポートで、上記判決のような文章を書くと、それだけで落第である。理由は初等物理が理解出来ていないということである。
ある空間内で、ある物体を考える。この物体にある力が作用したとき、物体内にはそれと同じだけの反力が発生する。反力が大きくなって、その物体が保持しているある力(これを仮に耐力と呼ぶ)を越えると、その物体は破壊又は大きく変形する。この時物体内に生じた力をF、力が働いた部分の断面積をAとすると単位面積当たりに生じた力uをその物体の強度と呼ぶ。
F=u/A
ところで、力にも色々種類がある。一般には
1)圧縮
2)引っ張り
3)曲げ
4)剪断
の4種類である。同じ物体でもそれぞれの力に対し発揮出来る力は異なるので、強度は力の性質に応じて使い分けなくてはならない。例えば、圧縮力に対しては「圧縮強度」、引っ張り力に対しては「引っ張り強度」という具合にである。被控訴人Bの主張や、原判決はこの点の区別・定義が出来ていないため、解釈に混乱が生じてしまったのである。
物体にも色々あって、例えば鉄やコンクリート、ガラスといったそれ自体で自立できる物体を「個体」と呼ぶ。これらに対しては上記4種の強度を物理的に定義出来、適当な試験を行うことによってその値を求めることが出来る。
では、土ではどうだろうか。土の代表的なものとして「砂」を採り上げる。砂は鉄やコンク-トのような個体ではなく、一つ一つの砂粒が集合した粒状体である。海浜や砂場で砂を盛り上げると、どうしても下図1)のような円錐状になってしまうのは誰でも子供の時代から経験済みである。
砂山の頂部から手で力を加えても、手がめり込むだけだから「圧縮強度」は求められない。砂粒の集合体だから、引っ張ったり曲げたり出来ないので「引っ張り強度」や「曲げ強度」も求められない。しかし、頂部に手で力を加えると下図2)のように一部から崩壊してしまう。この現象を剪断と呼ぶ。従って、砂の場合は「剪断強度」のみが定義出来る。
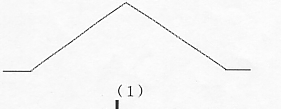 |
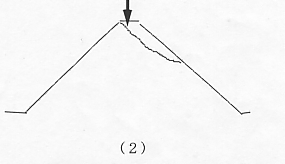 |
では、砂の剪断強度は何から決まるのだろうか。
砂に対して「剪断試験」というものを実施すると、砂に加えた垂直応力に比例して剪断強度が増加するという現象が見られる。これを「クーロンの法則」とよぶ。ちなみにクーロンとは電気力学でお馴染みのクーロンと同一人物である。
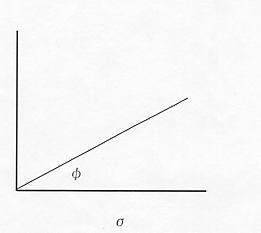 |
この時の垂直応力-剪断強度関係の勾配を「内部摩擦角」と呼ぶ。つまり、砂の剪断強度は固有の内部摩擦角φと垂直応力σの二つで決定される。これの意味するところは
(1)垂直応力が一定の場合φが大きい程、剪断強度は大きくなる。
(2)φが一定の場合σが大きい程、剪断強度は大きくなる。
つまり、φとσの二つの量を決めないと砂の剪断強度は決定出来ない。即ち砂には固有の強度というものが無い、ということである。
垂直応力σは実用的な場面では地表面からの土の有効重量に相当すると考えて良い。従って、これは剪断強度を求めようとする位置で変化する。結局、砂の剪断強度に関する固有の値とは内部摩擦角φということになる。φは何に関係しているかというと、大部分は砂の密度に関係しているということが、1930年代にTerzaghiらによって確かめられている。他にも要因はあるが、それらは特殊な場合に問題になるのであって、一般にはφは概ね密度から決定されると考えて大きな間違いではない。
従って、このような材料で構成されている構造物(例えば盛土)の安定性は最早、”強度”という単純な言葉で表されるのではなく、「すべろうとする力」に対する「抵抗する力」の比、即ち「安全率」という言葉で表される。
これまでが準備段階である。
3、不整形段差とテールアルメの強度の関係について
本不整形段差の発生原因については、控訴人・被控訴人で意見が分かれている。但し、これを追求することは本論述の目的ではない。不整形段差の発生が被控訴人主張通り、控訴人の施工不良によるもの(施工後に発生したとする)だとしても、その程度はテールアルメの安定性になんら関係しないということを証明することが目的である。
テールアルメは土(中詰め土)と鉄(ストリップ)の複合材である。コンクリートスキンは単なる前化粧であって、テールアルメの安定性には何ら寄与しない。つまり、”強度”に関係する部材は土と鉄しかない。テールアルメの設計手順では(1)ストリップの長さ(定着長)、(2)ストリップ間隔の決定が大きな要素をしめるが、これを決定するのは(1)中詰め土の内部摩擦角φと、(2)ストリップと土との摩擦係数である。後者も又、φに関係する。鉄の強度は一定であり、不整形段差が生じても変化しない。但し、定着長は変化する。従って、テールアルメの安定に採って決定的要素となるのは(1)中詰め土の内部摩擦角φと(2)ストリップ定着長ということになる。
以下、これらの要因の変化がテールアルメの安全性に採ってどの程度影響を与えるかを吟味する。
1)中詰め土の内部摩擦角φ
これは先に述べたように土の密度に関係するから、φの変化は不整形段差による密度の変化がどの程度のものであるかを調べればよい。
物体の密度は次式で表される。
ρ=W/V
ρ;密度
W;重量
V;体積
被控訴人主張通り不整形段差が施行不良によるものだとすると、施工後の不整形段差発生により密度が変化したことになる。段差発生前後の土の密度をρ1、ρ2、体積をV1、V2とする。重量は変化しないから密度の比は次式で表される。
|
n=ρ1/ρ2 =V1/V2 テールアルメ代表断面を右図のとおりとする。 V1=9.0×5.7+6.0×5.7=85.5m3/m 不整形段差により前壁が0.1m移動したとすると V2=9.1×5.7+6.1×5.7=86.64m3/m n=85.5/86.64=0.987 |
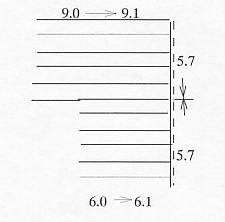 |
テールアルメ設計より、設計密度はρ1=1.9t/m3
一方、材料試験結果よりρt≧1.9t/m3という条件を満足出来る材料は試料1のみだからこれを中詰め材に使用していると考えられる(鑑定書p13)。これの施工条件下に於ける湿潤密度は1.947t/m3 である。従って、ρ2=0.987×1.947=1.922t/m3 ≧1.9t/m3となり、設計条件を満足する。
2)ストリップ定着長
0.1mの不整形段差発生によりストリップ定着長は0.1m短くなることになり、設計条件を満足しなくなる。では本当にそうなのだろうか。ストリップ長 Lminは次の手順で決定される。
|
(1) 内的安定計算により各段の引き抜きに対する最低定着長Leを求める。 (2) これに安全率2をかけたものを必要定着長Lrとする。 (3) Lrに自由長L0を加えたものをLminとする。 (4) Lminは端数を持つので、あるラウンドな数字に丸める。一般には0.5mラウンドである。例えばLminが4.7mであれば5.0mと いう具合である。本設計を見ると、0.5mラウンドのストリップ長は採用されていないので1.0mラウンドでストリップ長を決定したものと思われる。 |
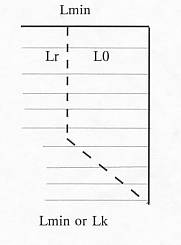 |
ストリップ長の決定は以上の様な煩雑な過程を経て決定される。この場合0.1mのような端数は、途中経過でLmin又はLkの中に包含されてしまう。従って、実質的に0.1mという定着長不足はテールアルメの安全性にとって何ら影響を与えない。
4、結論
以上述べた通り本テールアルメ壁面に見られた「不整形段差」は、テールアルメの”強度”低下には何ら影響を及ぼさない。従って、これをもってテールアルメ崩壊の一因とする被控訴人Bの主張、及びそれを採り上げ控訴人に施工瑕疵があったとする原判決は、”強度”という言葉の物理概念及びテールアルメ設計手法に対する理解を著しく欠き、且つ科学的・技術的合理性に欠けるものと結論される。
このことから、当鑑定人は「不整形段差」に関する、被控訴人Bの主張及び原判決は明白な誤りと判断する。
鑑定人 技術士(応用理学部門) 横井和夫