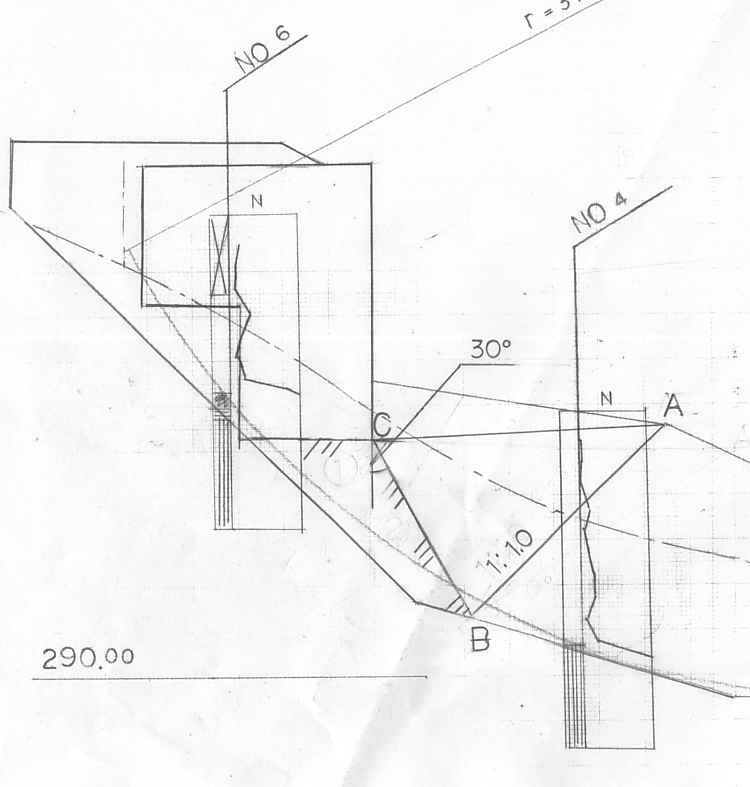 |
滋賀県某テールアルメ崩壊事故9(最期の闘争4thRnd)
さて、当方書面提出後、約一ヶ月した平成14年9月中旬、D社鑑定人のOからの、2回目の鑑定意見書が出てきました。又、10〜11月にかけて、他の被控訴人各社から、おそらくは最後の言い分と思われる、準備書面が提出されてきました。裁判所も、いい加減、痺れを切らし、云いたいことは全部云えと、各社に催促したからではないでしょうか。なお、被控訴人側準備書面は、従来の主張を繰り返すのみで、目新しいものはなく、全てを紹介すると、大変退屈になるので、O鑑定意見書(2)と、それに対する筆者の反論のみの、全文を紹介します。
なお、筆者の反論は、形式はO鑑定書への反論書になっていますが、実際はこれまでの被控訴人主張への全般的反論になっています。
先ず最初に、被控訴人Dの鑑定人である、O工学博士の鑑定意見を紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
B鉄工所滋賀工場テールアルメ崩壊事故原因に関する鑑定意見(2) 丁38号証
平成14年9月17日
工学博士・技術士(建設部門) O.N
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1、始めに
本書面では、控訴人が提出した二つの準備書面(平成14年8月12日付けと平成14年8月29日付け)に対する意見を述べる。
2、控訴人準備書面(平成14年8月12日付け)に対して
(1)降水量の解釈ミスと訂正
控訴人のご指摘のとおり、丁27号証において「月降水量」の扱いにミスがありました。失礼しました。そこで、大阪管区気象台で新たに調査した結果を以下に示す。
a)土山地区日降水量調査
アメダスによる1979年の1月から2001年12月までの23年間に於ける、日降水量の多い順に第1位〜第10位を表ー1に示す(丁39参照)
表ー1
| 順位 | 年月日 | 日降水量(㎜) | 備考 |
| 1 | 1995/05/12 | 231 | テールアルメ完成後 |
| 2 | 1990/09/19 | 201 | |
| 3 | 1988/08/16 | 188 | |
| 4 | 1982/08/01 | 177 | |
| 5 | 1994/09/29 | 174 | テールアルメ完成後 |
| 6 | 2001/08/21 | 173 | |
| 7 | 1994/09/16 | 163 | テールアルメ完成後 |
| 8 | 1990/11/30 | 152 | |
| 9 | 1992/08/19 | 150 | |
| 10 | 1997/07/26 | 149 |
表ー1より、平成7年5月12日に土山地区で降った雨はアメダスによる観測開始以来、平成13年12月までの23年間で最も多い日降水量(231㎜)であったことが判る。
b)彦根地区日降水量調査
彦根地区では土山地区と異なり、彦根気象台があるため、統計期間は1894年1月から2001年1月までの108年間となっている。この108年間に於ける日降水量の多い順に第1位〜第10位を表ー2に示す。彦根は土山地区と異なるが、最も近い気象台データとして参考とする(丁40参照)
表ー2
| 順位 | 年月日 | 日降水量(㎜) | 備考 |
| 1 | 1896/09/07 | 596.9 | 土山地区における95/05/12の日降水量231㎜は第2位に相当する。 |
| 2 | 1959/09/26 | 195.8 | |
| 3 | 1972/09/16 | 181.0 | |
| 4 | 1965/09/17 | 174.2 | |
| 5 | 1990/09/19 | 172.0 | |
| 6 | 1959/08/18 | 167.7 | |
| 7 | 1896/09/08 | 161.9 | |
| 8 | 1913/10/03 | 160.3 | |
| 9 | 1917/09/30 | 159.1 | |
| 10 | 1930/07/31 | 152.0 |
表ー2より、土山地区に於ける平成7月5月12日の降雨は、彦根地区の108年間の中で2番目に多い日降水量であったことが判る。以上より、土山地区の平成7年5月12日の降雨は、この100年間で最大級の降雨であったことが判る。
| この論法には、巧みな論理のすり替えがあることが判ります。先ず表ー2には、肝心の95/05/12の彦根に於けるデータがない。だから、土山のデータと比較のしようがない。アメダス観測以前に、95/05/12に匹敵する降雨があったかもしれないのです。しかし、雨が多いかどうかは、本質的な問題ではないので、見逃しても構わない。 |
控訴人は私のミスに対して、二の2において、「月降水量」という観点から平成7年5月の降雨は1.6年程度に1回発生する降雨と結論付けている。残念ながら平成7年5月の降雨はそのような程度の降雨では決してない。土構造物の崩壊に最も影響を与えるのは、「連続雨量」である。丁第27号証の3の(1)で説明しているように、「①当該現場がある関西・中国地方では、土構造物の崩壊までの連続雨量の平均値は210㎜程度であること、②関西・中国地方では2日雨量が210㎜になる確率は10年に1回程度である」との一般論に対して「当該現場では日降水量で231㎜、連続雨量363㎜」となっている。日降水量で231㎜がどの程度であるかは前述したとおりである。又、連続雨量363㎜上記の一般論に比較して、如何に凄い降雨であったかが判る。
控訴人は「月降水量」の大小が土構造物の崩壊に最も大きな影響を及ぼすかの如く結論付けているが、土構造物の崩壊に大きな影響を及ぼすのは、「月降水量」ではなく、「連続雨量」であり、それを構成している「日降水量」である。従って、控訴人が云う「平成7年5月」の降雨は1.6年程度に1回発生する降雨」であるという結論は、「月降水量」の観点からだけの結論であり、論争になっている土構造物の崩壊に関しては完全に間違いである。
更に控訴人が二の4において述べている「O
鑑定によっても、今回程度の豪雨で崩壊するのだから、仮に今回保ったとしても、砕石置換をしていても7〜8%の安全率増加では、増加しても安全率が1,01程度だから、確率的には、数年後には崩壊したとなるはずである」というまとめも根拠を失い間違いとなる。
以上より、テールアルメ崩壊の原因について以下の結論が導かれる。
今回のテールアルメ崩壊の原因は、地すべり地と豪雨であることはほぼ間違いない。簡単な図で表現すると次の様になる。
原因 結果
地すべり地 + 豪雨 ⇒ テールアルメの崩壊
図ー1
問題は崩壊原因としての地すべり地と豪雨の崩壊に与える影響がどの程度かということである。例えば、豪雨に関係無く地すべり地にテールアルメを施工している途中で崩壊したとしよう。この場合は崩壊原因の100%が地すべり地に設置したことになる。
原因 結果
地すべり地 ⇒ テールアルメの崩壊
図ー2
次に当該現場について考えてみると、地すべり地にテールアルメを築造したが、完成までは大きな変位等は発生しなかった。また、テールアルメ完成後の平成6年9月16日の大雨(日降水量163㎜は土山地区23年間で第7位の記録 表ー1参照)と平成6年9月29日の大雨(日降水量174㎜は土山地区23年間で第5位の記録 表ー1参照)では崩壊しなかった。この9月の大雨は23年間で第5位、第7位の日降水量であるが、両日が接近していることと、その間にも降雨があったことを考慮すると、土構造物に大きな影響を与える降雨であったことが判る。
最終的にテールアルメが崩壊したのは、平成7年5月12日の日降水量231㎜、連続雨量363㎜という、この100年間で最大級の降雨であった。以上より、当該現場に於ける崩壊原因の大きさを考慮して、図ー1を書き換えると次の様になる。
原因 結果
地すべり地 + 豪雨 ⇒ テールアルメの崩壊
影響小 影響大
図ー3
図ー3に示すように、当該現場に於けるテールアルメの崩壊原因は、前述したように地すべり地と豪雨であることには変わりはないが、地すべり地による影響よりも、豪雨による影響の方が大きかったということである。
平成6年9月の大雨に対しても崩壊しなかった。更にテールアルメのような土構造物は時間が経過するにしたがって安定性が増すことから、現場で砕石置換もしくはその他の対策が施されていれば、平成7年5月の大雨で崩壊することはなかったと考えられる。
(2)控訴人の主張に対する反論
控訴人の主張によると、二の5の1において、「本件テールアルメを地すべり地に建築し、必要安全率1.5を満たしていなかった。地下水位を考慮すると、砕石置換をしても安全率は1.01にしかならなかった。だから本件テールアルメは砕石置換の有無にかかわらず崩壊したのである。これ以上のことは云えないはずである。
土木構造物においては、最終安全率が必要安全率を満たしているかどうかのみが問題となるのであって、中間過程での安全率増加割合などは何の意味も持たないことは土木技術者として自明である。
地すべり地に建築したこと、必要安全率の計算を誤ったこと、いずれも明らかに設計ミスである」となっている。この意見について反論する。すべり安全率が低いのは既に丁27号証4の(3)砕石置換の効果(まとめ)で説明しているが、ここで再度説明することにする。
①先ず、安全率が低くなった原因は、崩積土の土質定数を求めるために横井鑑定人が実施した逆算法の「条件設定」にある。
②逆算法で崩積土の土質定数を求めるためには、崩壊後の斜面形状で、崩壊直後の地下水位を用いる必要がある。しかしながら、崩壊直後の地下水位は推定出来ない。そこで崩壊後1〜2カ月経過してボーリングしたときの地下水位を用いて計算している。崩壊後の8月、9月の雨量は少なく、計算に用いた地下水位は崩壊直後の水位線より相当低下していることが考えられる。
③地下水位が低下するとすべり安全率は大きくなる。しかしながら、どの程度大きくなるかは(地下水位の低下量が予測出来ず)推定できないので最低値の1.0を使用している。
④その結果として算出された崩積土の土質定数は本来の値よりも低めの強度を有していることになる。
⑤本来よりも低めの強度を有する土質定数を用いて、すべり計算を実施すると、すべり安全率は正しい値よりも低く算出される。
以上をまとめると表ー3のようになる
表ー3 逆算法の条件設定による影響
| 項目 | 正しい逆算法 | 実施した逆算法 |
| 地下水位の設定 | 崩壊直後の地下水位を使用する (但し当現場では推定不能) |
崩壊直後の水位を推定出来ないので、崩壊後1〜2カ月経過後の地下水位 を使用。 当然ながら崩壊直後の水位線より低下している。 |
| すべり安全率の設定 | 崩壊後安定した状態であるので1.0と設定 | 上記の水位線では安全率は1.0を越える。但し、1.1か1.3なのかは不明。結果 として不明なので1.0を使用。 |
| 算出される崩積土の 土質定数 |
正しい崩積土の土質定数が算出出来る | 正しい土質定数よりも低い強度定数が算出される。 |
| 崩積土の土質定数を 用いたすべり安全率 |
正しい安全率が算出される。 (真の安全率に近い) |
真の安全率よりも低いすべり安全率が算出される。 |
この土質定数を用いて地下水位を考慮した全体すべり(無処理)の安全率は0.94となった(丁27号証の4の(2)の表ー2参照)。この計算の地下水は崩壊時よりも低下したものを使用しているので、テールアルメ崩壊時の状況を想定していることになる。崩壊時よりも地下水位が低下している状態であれば、テールアルメは崩壊していないから、少なくともすべり安全率は1.0を越えている。しかし、Kの計算では0.94と1.0を大きく下回っている。これは何度も云うが、崩積土の土質定数を算出するための逆算法において、正しい条件設定が出来なかったためである。
控訴人は、「土木構造物においては、最終安全率が必要安全率を満たしているかどうかのみが問題となるのであって、中間過程での安全率増加割合などは何の意味も持たないことは土木技術者として自明である」と述べている。現場状況を正しく反映した計算により算出した安全率であれば、上記の意見は正しいが、今回のように正しく現場状況を反映出来なかった計算による安全率の場合には上記の意見は間違っている。
ここで、正しい条件のもとで、正しいすべり安全率を算出したとする。ここではその安全率を「真の安全率」という。真の安全率では以下のようになる。
・真の安全率<1.0
→ 崩壊する
・真の安全率1.≧0 → 安定している
当該現場のテールアルメのすべり安全率は崩壊した時点では、真の安全率は1.0を下回っていたのは事実である。しかしながら、砕石置換を施しておれば、安全率は7〜8%上昇していた。崩壊時の安全率を0.99とすると、砕石置換を施しておれば真の安全率は1.06〜1.07となり崩壊しなかった。この7〜8%(安全率では0.07〜0.08)が崩壊するか、崩壊しないかを決定付ける要因となる。(1)
(1)こういうことを云うから、日本の「博士」というのは信用されなくなるのだ。彼の云うことが如何に欺瞞に満ちているか!皆さんには分かりますか。結構、シロートは、こういう嘘に騙されやすい。
3、控訴人準備書面(平成14年8月29日付け)に対して
(1)控訴人の主張に対する反論(1)
控訴人の主張によると、2において、「設計図通りに掘り進んでいったが岩盤が出なかったので、A(施工業者)が、C(設計管理者)に対し、D(テールアルメメーカー)を交えて再検討したとしよう。この時に出る、唯一の結論は、もう砕石置換はやらなくてよいか、或いは、せいぜいもう少し掘って岩盤が出なかったら、そこまでで砕石置換は終了してよいという指示である。砕石置換以外の有功な対策工法が採用されることはなかったと断言出来る」とある。この意見に対して反論する。
このようなことは絶対あり得ない。地盤調査におけるボーリングはある間隔でしか実施しない。従って設計段階で100%地盤状況を把握するのは不可能である。当然ながら調査方法やボーリング本数等により、地盤の把握度合いは異なるが、どちらにせよある程度のところは推定せざるを得ないのが現状である。それを補うのが「施工」である。施工では調査と異なり、テールアルメを設置する範囲は全て掘削する。調査では判らなかったことがそこで判明する。勿論施工だけでも、100%地盤を把握することは出来ないが、少なくとも調査結果との相違は把握出来る。特に当該現場のように大きく異なる場合はなおさらである。
更にテールアルメの基礎地盤はボーリングによると、表土である砂質粘性土のN値は4以下の箇所がある。この程度の軟弱土であれば、バックホウで掘削している段階で地盤が軟弱であるとともに、このような地盤の上に10mを越えるテールアルメを構築するのは危険であることは分かる。当然ながらそれを判断するのはバックホウの運転手ではなく、A建設の現場責任者が判断するのである。何故ならA建設は建設業の許可を受けている施工会社であるからである。
Dも設計時に想定した地盤条件と大きく異なることが判れば、この段階で追加ボーリングを依頼するとともに、その結果を基に安定計算や対策工を検討することになる。控訴人が云うような対応は絶対にないと断言出来る。
更に「なぜなら、Dの安定計算では、本件崩壊部分は、砕石置き換えをしなくても、常時で1.5(最低で1.931)、地震時で1.2(最低は1.507)という必要安全率を優に越えているからである。そもそも本件崩壊部分においては、砕石置換は余計なのである」と続いている。
これも前述したように、現場の状況とは異なる設計条件をもとに安定計算をした結果であり、設計条件が異なれば、当然ながら再計算を行い、対策工を検討することになる。現場状況を正しく把握した設計条件では、砕石置換は適切な対策工とは云えず、その他の対策工が検討されると考えられる。
(2)控訴人の主張に対する反論(2)
砕石置換の範囲及び方法の件で横井鑑定人と私(O)では意見が異なっている。横井鑑定人によると、「O鑑定では砕石置換部を正勾配(下に行くほど幅が広くなる)としている。これでは安定計算上安全率が大きくなるのは当たり前である。しかし、下向きに断面を拡大して掘り下げることは、上から土が落ちてきて出来ない」更に、「正勾配で施工するのは不可能だから、逆勾配で切り下げ、その中を砕石で置き換える事になる」となっている。
横井鑑定は本当に下向きに断面を拡大して掘り下げると考えているのだろうか?(1)
ここでは、砕石置換の範囲決定とその施工方法について述べる。
テールアルメに用いる砕石置換の範囲を決定する場合、基本的には従来のコンクリート擁壁と同様の方法で範囲を決定する。
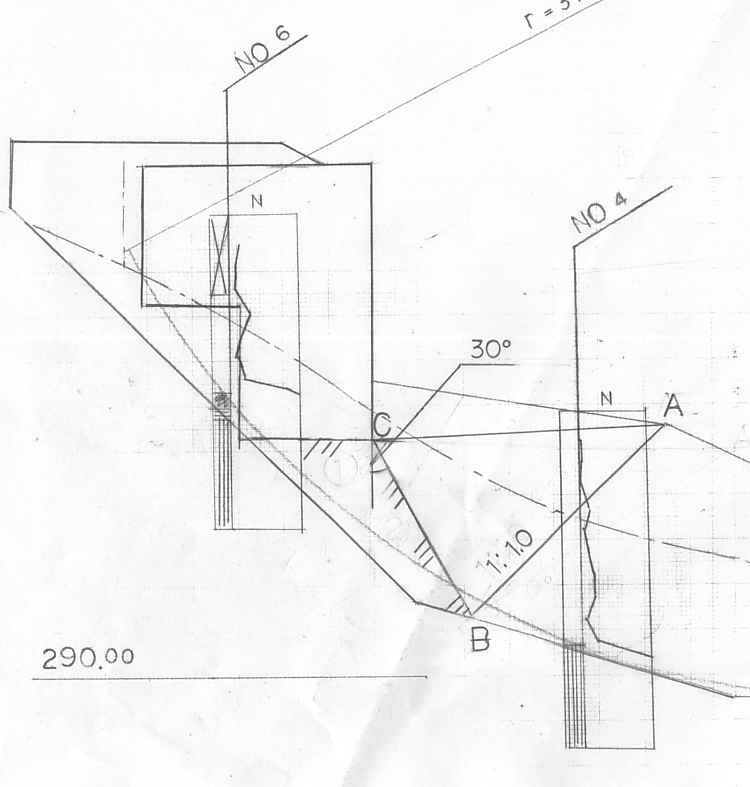 |
図ー1
テールアルメに用いる砕石置換の目的は次の二つである。
①テールアルメ基礎部を砕石置換することにより、沈下をなくす(もしくは減少させる)。
②テールアルメを含むすべり安全率を上昇させる。
上記の目的を達成することと、テールアルメの盛土荷重は基礎地盤では正勾配で分散していることを考慮して砕石範囲を決定している。
次に施工方法であるが、図ー1のA点より掘削して、B点まで掘削する。この時の掘削勾配(A・B)は地山の掘削安定勾配である。テールアルメ背面側も同様の掘削を行うが図では省略する。その後、掘削底面より1層30㎝以下毎に砕石と埋め戻し土を用いて、盛土(埋め戻し)していく。丁41号証のように、掘削した部分を全て砕石で置き換えないのは、△ABCの範囲に砕石で置換してもすべり安全率の増加に対して効果が少なく、図ー1のb)で示した置き換え範囲に於けるすべり安全率とほとんど違わないためである。
今まで、テールアルメの基礎地盤に砕石置換を数多く実施してきたが、このような現場状況では横井鑑定人のような砕石置換は実施したことがない(2)。施工方法、砕石置換の効果から考えてもこのような砕石置換は絶対にしない。
(1)私だってこんなやり方するわけはない。チョットからかってやっただけ(O工学博士の安定計算は正しいか?)なのに、向きになって反論してくるのだから、長野県人というのは、真面目というか、アホというか?何故、からかわれたか!肝心のO鑑定計算の解析断面図に、上記(A・B)の掘削線や埋め戻し土が、入っていなかったからだ。このような単純ミスをするから、つけ込まれるのである。それさえ入っておれば、幾ら横井技術士がいたずら好きでも、あのようなイチャモンは付けない。イチャモン付けられるのは、それだけの隙があるということ。設計では、線一本でも馬鹿には出来ない。線一本をミスって、会計検査につかまり、会社を潰しかねないことになった例は腐るほどある。
(2)普通なら、私だって、こんな置き換えはしないでしょうな。被控訴人が砕石置き換えに拘るから、こういう馬鹿げた絵が出てくるのだ。その原因が誰にあるのか、という点が問題。
私が不思議に思ったのは、このO工学博士は、しばしば、「・・・・のようなことは絶対にしない」と宣言することだ。いい年(この当時で56才ぐらいだろう)して、「絶対」などという後に退けない言葉が良く出るな、と思ったのだ。よっぽどの自信家か、それとも世間知らずのアホか、いや、スポンサーのDにねじを巻かれているのだろう。
次に、筆者の反論を述べます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
株B鉄工所滋賀工場テールアルメ崩壊事故未払い工事代金請求訴訟
O鑑定書(2)の問題点
鑑定人 技術士(応用理学)
地すべり防止工事士 横井和夫
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1、始めに
平成14年9月に、本件被控訴人Dの鑑定人である工学博士O.N(以下O博士と呼ぶ)による鑑定書(2)が示された。本鑑定書は様々な点で問題があり、当鑑定人としては容易に受け入れることは出来ない。その中には今後の審理に影響しかねる部分もあるので、敢えてここで反論することにする。
1)①本崩壊は地すべりが主か豪雨が主か。②地すべりは100年に1度の大雨でなければ生じないのか。
2)①横井鑑定の剪断強度は過小評価か。②安全率の考え方は正しいか。
3)岩盤が出てこなかったとして、工法変更を行っただろうか。
4)地盤調査の考え方は正しいか
5)設計変更と地盤調査
以下、上記5点について検討し、小川鑑定書(2)に反論する。
2、地すべりは100年に1度の大雨でなければ生じないのか。
2−1)本崩壊は地すべりが主か豪雨が主か
O博士は鑑定書(1)に於いて、崩壊原因の素因として、「テールアルメを地すべり地に設置したこと」としている。この点については当鑑定人も異論はない。又、誘因について平成7年5月集中豪雨及び7月連続降雨とする点についても両者の見解は一致している。しかしながら、その後次のように言い換えて、地すべりより降雨の影響のほうが大きいとし、
(1)地すべりの影響が大きければ盛土施工中又は直後に崩壊したはずである。
(2)盛土後数回の降雨にあっても1年間は崩壊せず、5月降雨により崩壊した。
(3)これは地すべりよりも降雨の影響のほうが大きく、採石置き換えを行っておれば崩壊を防ぎ得た。
と主張する。これは全く奇妙な議論である。小川博士は地すべりというものをよく理解せず、当鑑定人による鑑定書(甲第60号証)をよく読んでいないのだろう。
1)(1)について
これは、地すべりと軟弱地盤盛土とを混同した議論である。地すべりの場合、崩壊間隔が大きいと、その間にすべり粘土の再圧密が行われ、強度が増加する(地すべりによる攪乱ですべり面強度は一旦低下するが、時間が経過するとそれが回復するという意味)。又、応力の変化が小さい場合は必ずしも瞬時に崩壊するとは限らない。本件テールアルメは地すべり頭部に偏って構築されている。従ってテールアルメ荷重はすべり面全体には伝わらない。すべり面全体での応力変化は極く僅かである。そのため構築後はある程度安定する。
本テールアルメの設計に基づいて最大基礎地盤反力を求めると次のようになった。
〇ケース1(地下水位無視…テールアルメ立ち上がり直後) Qmax1=45.13t/㎡
〇ケース2(地下水位考慮…崩壊時) Qmax2=47.47t /㎡
基礎地耐力は、傾斜地盤を考慮してMeyerhof式によって概算してみると。
〇ケース1 qd=85.45t/㎡>45.13t/㎡(Fs=85.45/45.13=1.89<3.0)
〇ケース2 qd=41.05t /㎡<47.47t /㎡(Fs=41.05/47.47=0.86<1.5)
Fs;安全率 qd;極限支持力
つまりテールアルメ立ち上がり直後(ケース1)では、基礎地盤にはすべり破壊は生ぜず、テールアルメは自立する。これは安定計算に於ける、局所すべり・無処理・地下水位無視のケースに該当する。しかし、長期に対する安全率3を満足していないので、長期的な安定は保障出来ない。テールアルメは施工とともに沈下を生じる。但し、地盤は軟弱地盤ではないので沈下は早期に終了する。従って、テールアルメ築造後自立していたからといって、地すべりの影響が少ないとは云えない。
2)(2)について。
平成6年の西日本は記録的な干天続きであった。山地の地下水位は十分低下する。テールアルメ築造後、秋に2度ほど降雨があったが、これで地すべりが発生しなかったのは地下水位の上昇が危険レベルに達しなかったためであろう。従って、この間に地すべりが発生しなくても不思議ではない。つまり見かけの安定は保たれ得る。しかしながら地下水の蓄積は行われる。
3)(3)について
上記の安定はいわばぎりぎりの状態である。この状態に、大雨によるすべり土塊内の間隙水圧上昇が加われば、安定は簡単に壊れてしまう。当鑑定人は鑑定書(甲第60号証)p−14で本テールアルメの崩壊原因を「直下の岩盤の谷状地形と、それに堆積した厚さ数〜10m以上に達する崩積土を素因とし、平成7年5月12日集中豪雨、同7月3日〜6日にかけての連続降雨を誘因とする地すべりを原因とし、それに引きずられる形での二次的崩壊である」と結論している。これを模式的に描くと下図のようになる。
つまり①素因である崩積土があっても、誘因となる降雨がなければ地すべりは発生しないし、逆に②崩積土がなければ降雨があっても地すべりは発生しない。
O博士は崩壊原因を「地すべり」+「大雨」=「崩壊」という単純計算式で示し、大雨の影響が大きく、従って採石置換をすれば「安定」する、という単純な結論を出しているが、何故採石置換しておれば大雨がきても安定するのかという説明が無い。具体的な根拠が示されていないのである。実際の現象は、上図のように素因・誘因が互いに関連しながら進んでいく。どちらの影響が大きい、小さいとは云えない。物事の順序を考えなくてはならない。
O博士の主張(これは被控訴人Dによる従来の主張に沿うものであるが)によれば、採石置換をしておれば、大雨がきても地すべりは発生しないということになる。しかし、 素因が解消されない限り大雨が来れば、いずれ必ず地すべりは発生する。地すべりの素因を有する斜面上部に、高さ14mに及ぶ垂直盛土を計画し、その基礎処理を採石置換という安易な手法ですまそうとする考えそのものに設計上の欠陥がある。
2−2)地すべりは100年に1度の大雨でなければ生じないのか。
O博士は、控訴人代理人の調査による過去100年間の降雨統計の解釈について
とする。
平成7年5月12日降雨が、過去100年の間で希な大雨であったことには、間違いはないだろう。しかし、希な大雨や、100年に1度の大雨でなければ、地すべりは生じないということにはならない。
一般に地すべり・崩壊を発生させる降雨には次の二つのパターンがある。
(豗)突発豪雨型…短期間の集中豪雨で発生するタイプ。
(豩)長雨型………単日の降雨量は少ないが、数日又は数週間に渉って降雨が継続するタイプ。
何れも連続降雨量が災害発生に大きく影響する。
今回の崩壊過程をもう少し詳しく見てみよう。
①平成7年5月に最初の集中豪雨があった。降り始めは5/11で5/16に止んでいる。累計降雨量は363㎜、最大日降雨量は5/12の231㎜。時間最大降雨強度は36㎜/hである。この間の沈下量は161㎜である。
②この後沈下は進むものの、沈静化の傾向を見せている。
③6/13〜6/14にかけて累計98㎜の降雨があり、やはり120㎜の沈下が生じている。
④その後継続沈下が生じる。これには累積傾向が認められる。
⑤7/1より降雨が始まり、7/6にほぼ止んでいる。この間の累計降雨量は270㎜、崩壊前日の7/5までの累計降雨量は223㎜、最大日降雨量は7/4の83㎜である。
明瞭な累積沈下が始まったのは、6/14以降である。6/14から7/15までの先行降雨量は約370㎜である。5月中旬降雨による変状が(豗)突発豪雨型に、6月中旬降雨以降の変状が(豩)長雨型に相当する。つまり、日降雨量が極端に大きくなくても、長雨が続けば地すべりは生じ得るし、そういう現象は、100年に1度よりも短い間隔で、起こり得るということである。
更に、本斜面では、本件崩壊のおおよそ20年前に地すべりが発生したと云われる。これは甲第45証で見られる、斜面内の樹齢から推測される値とほぼ一致する(甲第60 号証 P10)。従って前回の地すべりは1975年前後となる。関係者の記憶も正確とはいえないので、前後2〜3年の範囲で主な日降水量を丁第40号証より読みとる。
○1972/9/16 181㎜
○1973/4/17 64.5㎜
○1974/4/8 72.5㎜
○1976/2/29 47.0㎜
観測地点が彦根で土山とは異なるが、土山のデータが無いので致し方ない。しかし、少なくとも1975年前後では、目立った降雨が認められないのも事実である。従って、100年に1度の降雨がなくても、地すべりは発生し得るのである。これの詳細検討には当該地すべりの履歴の検討が重要であるが、一般には、規模の小さい地すべりほど、再発間隔は小さいと思って良い。
3、①横井鑑定の剪断強度は過小評価か。②安全率の考え方は正しいか。③両者で安全率が異なる理由
3−1) 横井鑑定の剪断強度は過小評価か
O博士は横井鑑定の難点として次の点を挙げている。
O博士は各種証拠を熟読していないのではないか。採用した地下水位は、被控訴人D提出による丁第7号証の1〜10に基づいており、当鑑定人が任意に選択したものではない。
仮に崩壊直後、正しい地下水位が得られたとしよう。それは当然、本鑑定解析で用いた地下水位より高いことが期待される。しかし、その時の安全率は1.0以下であり、逆算強度はO博士の云うように、本鑑定解析で得られた値より大きくなるとは限らない。重要なことは最終結果としての安全率である。小川博士の主張に従えば、この時の地下水位は「崩壊直後の正しい地下水位」を用いなければならない。この解析に用いる地下水位は、「1〜2ヶ月経過」の値よりは高いから、結局求められる安全率は、当初安定解析の結果と全く変わらなくなる。もし、小川博士が当鑑定人の逆算強度に不信を抱くのなら、別の方法で強度を求め、それを提示すべきである。
当鑑定人の逆算強度は、崩壊後のあらゆるデータを考慮して決定しており、今後これ以上の値が得られる見通しは無い。
3−2)安全率の考え方は正しいか。
土木工学というものは何らかの材料を用いて、目的に応じた構造物を構築する技術体系である。使用する材料は、それぞれ固有の強度その他の物性値を有する。又、構造物は原則として、構築段階ごとに絶対的な安全性を要求される。一方、材料物性値は、製造工程での信頼性や強度が、応力によって変化する等の不確定性を含む。そのため設計に当たっては、固有強度を低減した許容値を採用する。即ち、構造物各部で発生する応力や変位をこの許容値以下に収めることによって、構造物の安定性を担保する。
一方、土のような粒状体は固有の強度というものを有しない。従って、盛土・切土のような土構造物の設計では、すべり安全率で安定性を評価する。
O博士はこの件に関し、「真の安全率F1」が求められるものとし、
F1≧1.0の時安定
F1<1.0の時不安定
であるとする。従って、本件テールアルメ盛土で、「採石考慮、地下水位考慮」のケースで、F1=1.01 ≧1.0故安定するとし、被控訴人D代理人も、「安全率が1以上であれば外的安定が保たれて崩壊しないが、その値が僅かでも1を下回ると外的安定を失って崩壊する。安全率とはそういう概念である(被控訴人D 平成14年10月31日付け準備書面P5)。」と主張する。まさか、当鑑定人としては、法律家から「安全率」の講義を受けるとは夢にも思わなかった。ここでは、どうも「安全率」という言葉の解釈に混乱があるように思われる。従って、問題点を整理しておく必要がある。問題点は次の2点である。
1)「真の安全率」が求められるか。
2)「真の安全率」が1を僅か上回っていたとして、それが長期的安定性を保障し得るか。
1)「真の安全率」が求められるか。
「真の安全率」を求めるために、は土の「正確な剪断強度」を求める必要がある。地すべりのような不均質な地山に発生した、すべり面の強度は一様ではなく、場所によって大きく変化する。「正確な剪断強度」を求めるためには、すべり面上で細かい間隔で乱さない試料を採取し、正しい試験方法で剪断強度を確認する必要がある(例えば1.0〜0.5mピッチというように)。更にそれを統計的手法で処理した上で、安定解析を行うのである。それに要するコストを考えれば、これが非現実的なものであることは顕かである。この点を現実化するために、すべり面強度が一様であると仮定した解析法が用いられる。今回用いた逆算法はその代表的なものである。
2)「真の安全率」が1を僅か上回っていたとして、それが長期的安定性を保障し得るか。
この考え方はもはや技術ではなく、奇術・曲芸の世界である。曲芸の中に剣やコップを垂直に重ね、回転させたり、飛び物を受け取ったりするものがある。これはコップや剣に働く重力や、互いの接触面での摩擦力バランスを極限まで追求した技であり、物理的には理にかなっている。列が完成したときの、コップや剣列の安定性を安全率で表現出来るとしよう。完成したときの安全率は1.0を僅か上回っている。これが1.0に近づけば近づくほど、技の完成度は高い。但し、この技が完成するためには次の3条件を満足する必要がある。
(1)パフォーマンス会場は絶対に風が吹かない屋内であること。
(2)観衆に余計な振動を発生させないこと。この種の技は、パフォーマーにとっても極度の精神集中が必要である。観客がざわつけば精神集中の邪魔になるし、雑振動は全体のバ ランスをとる上での障害にもなる。これを防ぐために、観客にも精神集中をさせることが必要になる。そのためパフォーマーは、前口上を入念に仕立て、観衆の注意を舞台に引き つける。
(3)この種のパフォーマンスは、いわば瞬間芸であり、長続き出来ない。そのため全体パフォーマンスの最後に演じる。
つまり、この技は極度に人工的に製作され、且つ管理された理想的な空間でしか、実現不可能なのである。僅かでも風が吹けば、全体のバランスは簡単に崩れてしまう。小川博士や被控訴人Dの主張は、まさに「理想的な空間」でのみ通用する話しである。
現実の土木構造物で、そのような理想的な空間はあり得ない。更に、長期的永続性が要求される。構造物の安定性には不確定な要素が多く、特に解析に当たっての地盤モデル・地盤物性値には、種々の要因で不確定要素が入る。又、安全性限度一杯の構造物では、使用に当たって必ず不安要素がつきまとう。一体どの世界に「あなたの家の安全率は1.0ぎりぎりですよ」と云われてその家を買うようなお人好しがいるだろうか。
安全率1.0ぎりぎりでは、なお何時崩壊するか判らない危険性があるため、設計においては余裕を持たせた安全率を用いる。これが計画安全率又は必要安全率である。通常の切土・盛土の設計では安全率を1.2(日本道路公団「設計要領第1集」他)〜1.5(宅地造成規制法)とすることが多い。少なくとも1.05以下というものはない。テールアルメの設計では常時1.5、地震時1.2を用いるものとしている。これはこの安全率を満足すれば、テールアルメ業界が、使用者(事業者、施工者)に対して安全性を保障するという意味である。安全率が必要安全率と1.0の間ではなお、危険要因が考えられるため、この範囲での設計は不可(安全性を保障出来ない)とされる。
|
(1)大規模地すべり対策では、経済性の観点からFs=1.05で、対策工を設計することはある(河川協会「河川砂防技術基準」、道路協会「道路土工・(のり面工・斜面安定工指針)」。しかし、これは特殊なケースで国土交通省直轄工事でも本省協議が必要になる。まして民間工事ではあり得ないケースである。本件地すべりはこれに該当するほど大きい規模ではない。 (2)施工中・後の計測や管理で安全性が担保されれば、必要安全率以下でも事業が認可されるケースはある(日本道路公団のみ)。但し、安全率1.0以下は不可。 |
通常の土木工学の世界では、Fs=1.01や1.02程度で、「安定である」とはしない。この程度の安全率では、僅かでも条件が異なれば、簡単に安全率は1.0を割ってしまう。そのため、「安全率は著しく不足しており更なる対策が必要である」と判定され、評価の対象にはなり得ないのが常識である。
従って、「計算安全率が僅かでも1.0を上回っておればそれで安全である」という主張は、現在の社会通念(現在の土木工学の体系、国や学会等による設計諸基準)を全く否定するものである。
採石置換を行った場合でも、安全率1.0に対する余裕は横井鑑定では0.1%、小川鑑定でも僅か1%である。これではとても安全性を保障し得ているとは云えない。業界の保障基準である必要安全率を満足しない製品は、欠陥製品としか云いようがない。
更に、O博士が主張するように、真の安全率を僅かでも上回れば安全であれば、テールアルメでの部材応力度も限界値を使用して良いはずである。例えばストリップの引っ張り強度には210MN/㎡を使用して良い。しかし実際には、許容応力度として140MN/㎡を使用している。O博士の論法に従えばこれは過大設計になるのではないか。まして、対策工実施後の安全率は1.5を越えている(甲25号証 p11〜12)。これは設計に当たった被控訴人C並びにD自身が、必要安全率1.5を念頭に置いた結果である。これもO博士や被控訴人Dの主張によれば過大設計になるのではないか。
つまり、O博士や被控訴人Dは、採石置換効果を強調したいあまり、様々な点で自己矛盾に落ちいっているのである。
3−3)両者で安全率が異なる理由。
O鑑定と横井鑑定で安全率が異なる理由の大部分は、採石置換幅が異なるためである。小川鑑定ではストリップの補強効果を加えているとしているが、これはプログラムやデータ上の話で、実際の破壊臨界円は、補強部分の外側を通っているので計算結果には反映されていない。
O鑑定では正勾配で置換する。それに対し横井鑑定は、テールアルメ基礎端から垂直に下ろした線の内側を置換する。当然置換幅はO鑑定の方が大きいから、大きい安全率が得られる。実は当鑑定人も、当初小川博士と同様の正勾配を用いようと思った。しかし、いざそれを図面上に展開すると、掘削量・置換量がともに余りにも膨大なものになり、とても置換と言えるようなものでは無いことが判った。それは博士作成の断面図(丙33号証乃至丙38号証P8)を見れば一目瞭然である。そのため土留めクイ併用の垂直置換に切り替えたのである。
O博士の方法は規模から見て、もはや単なる採石置換ではなく別個の工事である。このような莫大な費用を要する工事を行っても、安全率は僅か数%しか向上しない。O博士や被控訴人Dは、安全率1.001と1.01の差をことさらに大きく取り上げているが、これは理工学の世界では全く「有意な差は無い」とみなされるレベルのものである。即ち、これは採石置換が、工学的に無意味であることを示している。要するに、O鑑定は採石置換が工学的に効果が無いことを再確認したにすぎない。
そもそも、本件地すべりは、採石置き換えをしていなかったから発生したものではない。当鑑定人が本鑑定書(甲60号証 図9−2)、平成14年5月27日付け検討書(甲号証 図−5)で既に示したように(甲 号証はその後控訴人Aから提供された現場記録写真を基に甲60号証を修正加筆したもの)、地すべり引っ張り亀裂はテールアルメの外側に斜面頂部全体に発生し、且つ斜面末端に隆起が生じている(周辺の引っ張り亀裂や斜面末端隆起がテールアルメの押し込みによるものではないことは、当鑑定人が甲60号証で証明済みである)。これらのことは、テールアルメ周辺の斜面全体が、テールアルメとは無関係に自律的に地すべりを生じたことを意味している。一方、採石置換工法とは、採石そのものに自立性がないから、周囲の地盤が動かない…つまり採石が、周囲の地盤により恒久的に拘束されている条件でのみ有効な工法なのである。採石置換部外周の崩積土が、地すべりを生じ周囲の拘束が解ければ、46t/㎡もの荷重を受ける採石が自立出来るわけがない。従って、テールアルメの崩壊は避けられない。これはもはや、1断面に於ける安全率が1.0を上回っているかどうかという問題ではなく、斜面全体の性質から決定される現象である。
小川博士並びに被控訴人Dの主張は、実際に生じた現象の本質を無視し、安全率という些末な問題を誇大に取り上げ、議論を矮小化しようとするものとしか受け取れない。
4、岩盤が出てこなかったとして、工法変更を行っただろうか。
この問題について、O博士は鑑定書(1) で「⑤施工者が設計図通り、『テールアルメ基礎は、岩着ないし岩に達するまで採石による置き換え処理をする』を厳守して施工すれば、いくら掘削しても岩盤が出てこない状況に遭遇する。当然ながら計画と異なる現場状況を、施主や施工管理者に報告する義務があった。もし報告しておれば、そこで再検討を実施することになり、計画の置換採石とともに、その他の対策工法が検討され、今回のような崩壊にはいたらなかったと考えられる」(丁26号証P8)と主張する。実際の工事現場では殆どサーカスのようなやり方である。
これに対し、控訴人代理人は平成14年8月準備書面で
(1)Dはテールアルメ販売を主たる目的とする営利企業であること。
(2)当初設計では採石置換を行わなくても必要安全率を優に越えている。
(3)他工法を採用すればDにとって減額査定になり、更にボーリング等を追加すれば大幅な工期延期になる。
等の要因から、「仮に、設計図どおり採石置換をしたが岩盤が出てこなくて、A・D・Cで話合ったとしても、他の工法が採用されることはなかった」とした。
これに対しO博士は更に鑑定書(2)で、「Dも設計時に想定した地盤条件と大きく異なることが分かれば、この段階で追加ボーリングを依頼するとともに、その結果をもとに安定計算や対策工を検討することになる。控訴人が云うような対応は絶対に無い」と明言している(丁第38号証P6)。しかし、本当にそのようなことは「絶対にない」のだろうか?。事実と突き合わせて検証する。
4−1)被控訴人Cの指示の有無
控訴人A従業員藤橋の証言によれば、「テールアルメの中央部で掘削したが岩盤が出なかったので、その旨設計管理者である被控訴人C馬場に報告したところ、『そのままでよい』という指示を受けた」とされる(平成11年10月25日 人証p11)。
ここで重要なことは、基礎面まで掘削した時点で、岩盤が出なかった場合、岩盤が出るまで掘削せよ、という指示が出たか否かである。
被控訴人Cは、平成14年9月12日付け準備書面で、藤橋証言を否定し次のように述べている。
「なお、控訴人は、Cの従業員馬場が、採石置き換えをしないでよいと指示したと主張するが、馬場自身は明確にこれを否定しているし(丙第21号証3頁)、そもそも、控訴人がその根拠とする控訴人従業員藤橋の証言は、本件崩壊部分とはかけ離れた崩壊していない箇所についてのものであって、…」。
場所が変わっていようがいまいが、岩盤が出なくても「そのままでよい」という指示があったのは間違いない。更にこの地点では、追加掘削やボーリングを行えという指示が無かったのも事実である。従って、控訴人A従業員藤橋が、その後も、岩盤が出なくても原設計どおりで施工して良いと思いこんでもやむを得ない。仮に、藤橋が崩壊斜面部で「岩盤が出ない」という報告を行った場合でも、被控訴人Cの対応はどうであったかと考えると、他区間と同様「そのままでよい」という回答以外にあり得ない。何故なら、他区間では「そのままでよい」とし、当該崩壊斜面で「追加掘削を行って地盤を確認」せよという指示は、当該崩壊斜面の地盤を、他とは異なる不安定なものであるという認識がなければ出る筈がないからである。この点を以下に検討する。
4−2)被控訴人Cによる地盤の認識
被控訴人Cは、「地形・植生から容易に地すべり斜面と判定し得る」という当鑑定人の意見をことごとく否定し、次のように述べている。
①「山腹崩壊危険度判定表」から「調査地の斜面安定度を+1弱と考え現況斜面の健全度は特に問題なしと判定した」(丙22号証 P3)。
②「崩壊地斜面の等高線形状が他の斜面と大きく異なり、特に地形上の特異性として捉えるには可成り無理があり、過大評価と謂わざるを得ない。又、崩壊地付近の北側斜面に円錐状を示す小規模な等高線の形態は認められるが、崩壊していない健全な斜面の地点であり、なお平坦部に大きく開ける斜面端部は、必然的に不鮮明になるのは当然であり、これを以て地すべり斜面と評価するには、また可成り無理があると謂わざるを得ない(丙32号証 P1)」。
③「…、何故ならば、地すべりの発生する規模は1〜100haと大きいもので、その痕跡は広範囲に至るものである。なお、復旧工事の施工写真から明らかなように崩壊箇所で崩積土が被覆している地盤状況が目視出来ない。これを局所的な現象として捉えるならば、人工的な捨て土以外考えられなく、自然地形ではあり得ないことである(同上 P2 )」。
*なお、捨て土上に盛土するなど、もっての他である(鑑定人意見)。
④「…しかしながら、本件崩壊場所は、滋賀県からも何ら地すべり防止区域にも地すべり危険個所にも指定を受けておらず(丙第22乃至30号証)、仮に万一本件崩壊場所が地すべり地であったとしても予見し得なかったものである。…略…控訴人が控訴審になって始めたかかる主張は、学者の机上の空論に乗っているだけのことであって、仮に万一本件崩壊場所が地すべり地であったとしても、当事者誰もが予見し得なかったのは顕著な事実である(被控訴人C代理人 平成14年9月12日付け 準備書面)」。
*「当事者誰も」のなかには当然控訴人Aも含まれる(鑑定人意見)。
以上のことから、被控訴人Cは、崩壊斜面地盤を他区間(これには岩盤が出なかったにも関わらず「そのままでよい」とした区間も含まれる)と同等に見なし、安定性に何ら疑問を抱かなかったことは顕かである。又、被控訴人Dは、テールアルメ区間中央の谷部において、ボーリングの追加を被控訴人Cに要請していた事実はあるが(平成10年10月12日 人証(馬場吉昭)、丙1号証 P8)、当該崩壊斜面のみならず、山地部でのボーリングを一切提案していない。従って、被控訴人Dも又、崩壊斜面の地盤を安定と認識していたことには間違い無い。以上のことから本崩壊地のみを特別視することはあり得ない。
4−3)掘削面の地盤は当初想定と大きく変化していたか
O博士の主張の前提として、「掘削部の地盤が想定と大きく変化している」ことが現場で確認されていることが必要である。
被控訴人Cは「崩壊箇所の地盤特性」について、「…これは、テールアルメの施工位置(安定計算No3+20.0) で崩壊後のボーリング結果による岩盤線(鑑定意見書甲60の1)の復旧断面図B−B断面)と一致している。復旧工事での施工写真が示すとおり、崩壊部直近の掘削面では想定したとおりの地層状況が、また、斜面法先付近のテールアルメ底面地盤では砂岩層が確認されており、想定地盤とほぼ一致する(丙32号証 P1)」と主張している。
この点は当鑑定人もチェックし、部分々々では正しいことを確認している(平成14年5月27日付け検討書)。これを分かりやすく図示したものが図4−1である。
 |
図4−1で左の図は、Cによる想定地質断面と、崩壊後ボーリングによる地質断面とを重ねたものである。これでは両者による岩盤/土砂の境界は偶然A点で一致する。この状態が掘削面でどの様にに見えるかを表したものが右の図である。掘削面での岩盤/土砂の境界は想定とほぼ一致してしまう。少なくともB−B断面では一致する。
O博士の主張する、再度の安定計算や対策工検討は、追加掘削やボーリングが前提になる。更に、その前提となるものは、博士がいみじくも自ら述べているように「(掘削時に)設計時に想定した地盤条件と大きく異なることが分かる」ことである。 図4−1に示したように本崩壊部掘削面で現れた地盤状況は、想定と「大きく異なる」どころか、ぴったり一致してしまうのである。
|
なお、O博士は表層部にN値4以下の軟弱部があり、これはバックホウで掘削している段階で分かる、としているが当鑑定人にとっては、バックホウでN値が分かるというような話は寡聞にして知らない。又、表層の軟弱部は排土されてしまうから、テールアルメ基礎とは無関係になる。テールアルメに最も近接しているボーリングB−NO6地点では、テールアルメ基礎にかかる部分のN値は最低で8、最大18、平均すれば10前後である。 |
無論、O博士はこの点について、「これは飽くまで基礎掘削面での情報であって、横断的な情報を反映していないから、岩盤が出るまで掘削すべきである」と反論するだろう。しかし、掘削面での地盤状況が想定と一致しておれば、誰しも横断的にも当初想定と一致していると考えるのは当然なのである。
4−4)追加調査や他工法検討が行われる可能性があったか
従って、控訴人Aが仮に「岩盤が出ない」という報告を行ったとしても、又それを被控訴人Cが現場で確認したとしても、他の同様区間で「追加掘削やボーリングを行え」という指示を出していない以上、本崩壊斜面でも「追加掘削やボーリングを行え」という指示を出す筈がない。
これに対し、被控訴人らは「設計図面上で『岩盤までの採石置換』を施工条件として明示している以上、岩盤までの採石置換は施工者の義務である」と常に主張している(被控訴人C代理人 平成14年9月12日付け準備書面、丁第13号証P5〜6、他)。しかし、他区間ではこの義務を免除しているのである。何故、本崩壊区間のみこの義務を履行しなければならないのか。その点の説明が全く出来ていない。一旦、義務を免除した以上、それから発生するリスクは設計者が負担するのが当然である。
一方被控訴人Dは、自らを単なるテールアルメ部材の販売業者であると規定し、「Dが当該現場の地質情報を獲得する義務はない」(被控訴人D代理人 平成14年4月18日付け準備書面)、と主張する。従って、岩盤が出なかったときの対応は、被控訴人Cの判断・指示に追従することは間違い無い。設計者が共同して地盤に不安感を抱かず、まして当該斜面が地すべり地であることは、当事者誰もが予見し得ず、更に掘削面での地盤が見かけ上、想定と一致しているのだから、控訴人Aが地盤に不安を感じる筈がない。仮にボーリングを提案したところで、被控訴人Cにより拒否されたであろう。そうでなければ論理の整合性がとれない。
以上をまとめると
1)被控訴人Cは当初より当崩壊斜面を地すべり地と認知せず、地盤は安定なものと判断していた。当然、被控訴人Dも、控訴人Aもそれに追随する。
2)テールアルメ北壁中央部で岩盤を確認せずに「そのまま」テールアルメを施工した区間がある。ここでは追加掘削やボーリングによる地盤調査の指示はなかった。設計図面で 示されている「岩盤までの採石置換義務」はここでは免除されている。
3)本崩壊地地盤での掘削面に於ける地盤状況は見かけ上当初想定とほぼ一致していた。
4)従って、被控訴人Cや被控訴人Dにとって本崩壊地のみ追加掘削やボーリングによる地盤の確認を控訴人Aに指示すべき理由は存在しない。
5)控訴人Aにとっても追加調査を行うべき動機が存在しない。
これらの点から、控訴人代理人が主張するとおり、「追加調査や対策工検討が実施される可能性は全くない」、と考える方が合理的である。従って、O博士の鑑定書(1)、(2)での主張は全く論拠を失う。要するに、O博士の主張は被控訴人らの地盤に対する認識の甘さ、設計の欠陥を糊塗し、責任を控訴人Aに転嫁するための詭弁にすぎない。
更に、重要な点を挙げておく。被控訴人C、D並びにO博士は、一貫して基礎採石置換さえしておけば、テールアルメは自立し得たと主張している。これには採石置換工法が現実的に可能であるということが前提になる。一方、O博士は鑑定書(1)のまとめで「④また、控訴人A建設㈱が設計図の指示どおりに施工しておれば、基礎下8mにある岩盤まで掘削することが現実的に不可能であるため、再検討の結果、置換採石よりも有効な対策工が採用された可能性も高い」(丁第26号証 P8)としている。自ら採石置換工法を否定しているのである。一体どうすれば良いのだろうか。一方で採石置換をすべきとし、一方でこれを否定する。これほどの大きな矛盾はない。もし、別工法を採用すべきとしたならこれまでの被控訴人らの主張は全て瓦解することになる。
5、O博士の地盤調査に対する考え方は正しいか
O博士は地盤調査に関し「地盤調査におけるボーリングはある間隔でしか実施しない。従って。設計段階で100%地盤状況を把握する事は不可能である。当然ながら調査方法やボーリング本数により、地盤の把握度合いは異なるが、どちらにせよある程度のところは推定せざるを得ないのが現状である。それを補うのが『施工』である。施工では調査と異なり、テールアルメを設置する範囲は全て掘削する。調査では分からなかったことがそこで判明する。もちろん施工だけでも、100%地盤を把握することはできないが、少なくとも調査結果との相違は把握できる。特に当該現場のように大きく異なる場合はなおさらである」。
これは概ね、被控訴人Cによる「事前調査は概括的なもので、施工時の詳細を把握するものではない」旨の主張に沿ったものである。なお、技術レベルとしては、大学工学部学生対象の初等講義の域にとどまっている感は否めない。
これらの主張は、被控訴人C(と被控訴人D)による事前調査を正当化する主旨で行われたことはあきらかである。従って、ここでは先ず、事前調査がO博士他の主張に照らしても正当であるかどうかを検証する。
1)谷部のボーリング
延長340mに及ぶテールアルメ区間で4箇所のボーリングが行われている(丙第4号証)。これを断面的に表示すると図5−1のとおりである。
ボーリングは、全て丘陵を開析した谷上で、テールアルメにほぼ直行方向、にテールアルメ上下端を挟むように2箇所ずつ実施されている。この谷はほぼ直線で、地形の起伏にも乏しく、テールアルメの上下端で、土質が大きく変化するようには思われない。
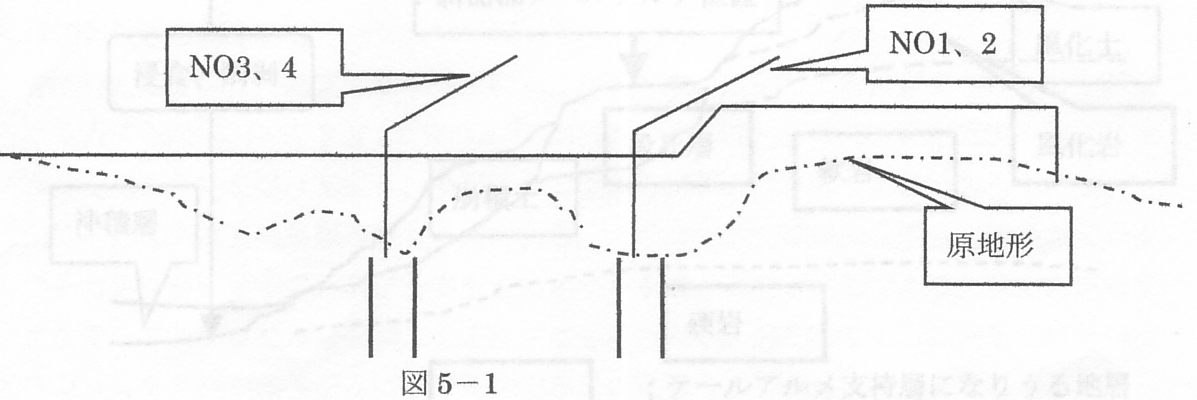 |
O博士らの論法に従えば、下流端で各1箇所のボーリング(NO1、3)を行い、そこで岩盤深度を確認すれば(上流の岩盤深度が下流より深くなることはまず無いので)、それを基に基礎底面位置を決定し、施工段階で確認しつつ施工すれば良いはずである。つまり、ボーリングNO2、4は無駄なのである。つまり被控訴人らは云っていることと全く反対のことをやっているのである。
2)丘陵部について
谷の両側に広がる丘陵部(正確には河岸段丘部(甲第60号証 P11ないし図7−1)には全くボーリングは行われていない。具体的な地質資料は全くない。
O博士の論法では、「施工」は調査の不足を補うものとして定義される。この場合は基準になる地質データが、少なくとも近傍で確保されていることが必要である。それと博士は掘削により全てが明らかになると勘違いしているようだが、「掘削で分かる」のは掘削面での情報のみである。その下のことは分からない。
丘陵部では基になるデータが全くないのだから、一体何を確認してよいのか分からない。判断の指標になるものがないのである。従って、丘陵部では計画的な施工は不可能で、いわばめくら滅法で施工をこなしていかなければならない。
これに対し、被控訴人らは「いや、4箇所のボーリングをやっているのだから、設計段階での地盤調査責任は果たしている」と主張するだろう。一審判決でも、この主張を受け、控訴人敗訴となっている。しかし、ボーリングは、丘陵部とは地盤条件が全く異なる、谷部でしか行われていないのである。ボーリングは設計目的や地盤の状況に応じて、適切に行わなくてはならない。
一般に山地や丘陵では、地質は同じであっても、風化の程度に応じて地表から(1)風化土→(2)風化岩→(3)軟岩→(4)硬岩というように、岩盤の状態が変化する。又、山地や丘陵斜面部では、本件斜面のように、河岸段丘や崩積土のような新しい堆積物が岩盤を覆って分布することがある。一方、谷部ではこれらは概ね削剥され、谷底にたまった新しい堆積物(いわゆる沖積層)とその下の岩盤のみが現れる。これを分かりやすく図示すると図5−2のようになる。
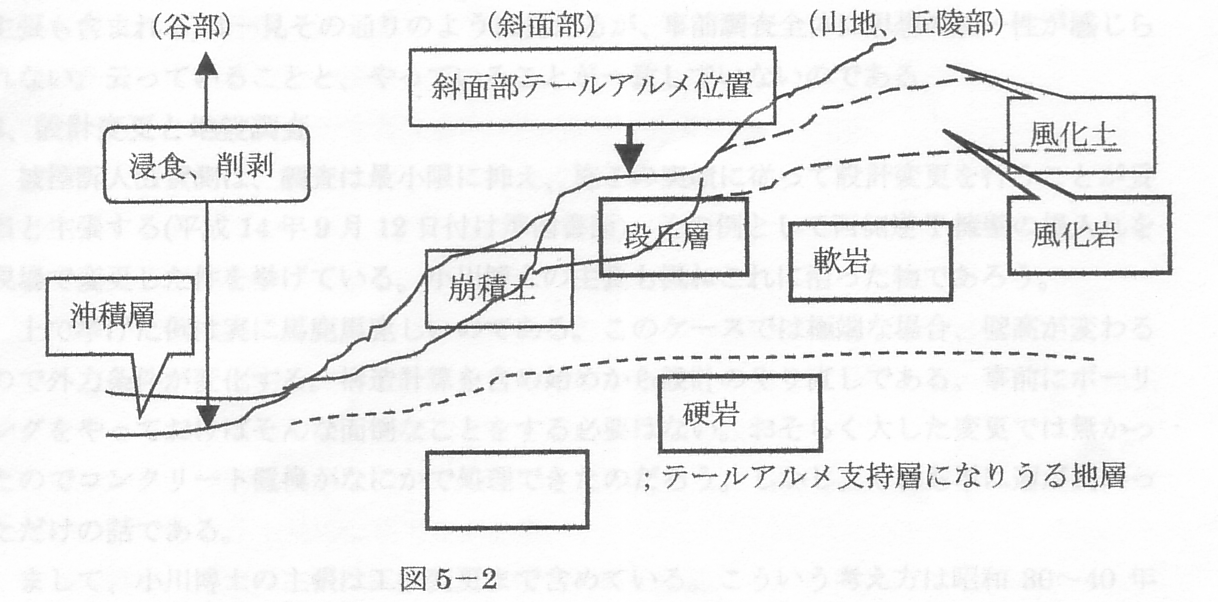 |
これらの厚さや分布状況は千差万別で一慨にこうだとは云えないが、要するに谷部のボーリングデータは、丘陵部には適用出来ないということである。
被控訴人らの主張するような、谷部でのボーリングを丘陵部での設計根拠にすることは、大阪での代表的な軟弱地盤に建っている、大阪法務合同庁舎の地盤データを、六甲山の山頂に適用するようなもので、ナンセンス以外の何者でもない。被控訴人Cらが行った事前調査は、概括的調査にすらなり得ていない。
|
丘陵部分でボーリングが行われていない点について、当鑑定人は当初、設計者が地山は岩盤だから、地盤は安定と判断したのだろうと善意に解釈した。しかし、次に横断図を見ると、テールアルメは3m近く根入れされている。岩盤であれば1〜2m程度で構わないのではないか。おそらく設計者は斜面の地盤に何らかの不安要素を感じ、根入れを大きくしたものと思われる。そうであれば、その点はボーリングで確認すべきであろう。何故ならボーリングによって不安要素が解消されれば、それが発注者の利益に繋がるのだから。 |
幸いにして岩着が確認されなかったのは、本件崩壊斜面を含め2カ所にすぎなかったが、これも単に運が良かっただけである。一方、丘陵部でも、表層を覆う段丘層は洪積層だから支持力は十分にある。段丘層を支持層とすれば、本件崩壊斜面を除く区間では、基礎の岩着や岩盤までの採石置換は不要で、且つ壁高をもっと小さく(テールアルメ根入れを小さく)出来た可能性がある(おそらく2m近く)。つまり、その分、工事費を低減出来るので、原設計は過大設計の可能性が疑われる。 ボーリングの根拠があって、基礎底面位置を決定したのであれば、このような余計な疑いをかけられることはない。
即ち、十分な調査は、経済的に見て不利であるどころか、全体工費からは経済的により有利になる。被控訴人C、Dの設計はその点でも瑕疵がある。従って、O博士の地盤調査に関する鑑定意見は、現実的な意味を持たない。O博士の主張(被控訴人Cの主張も含まれる)は、一見その通りのように見えるが、事前調査全体に思想の統一性が感じられない。云っていることと、やっていることが一致していないのである。
6、設計変更と地盤調査
被控訴人Cは、調査は最小限に抑え、施工の実績に従って設計変更を行うことが妥当と主張する(平成14年9月12日付け準備書面)。その例として西側逆T擁壁の根入れを現場で変更した件を挙げている。O博士の主張も概ねこれに沿った物であろう。
上で挙げた例は、実に馬鹿馬鹿しいのである。このケースでは極端な場合、壁高が変わるので外力条件が変化する。構造計算を含め、始めから設計のやり直しである。事前にボーリングをやっておけばそんな面倒なことをする必要はない。おそらく大した変更では無かったので、コンクリート置換かなにかで処理できたのだろう。しかし、それも単に運が良かっただけの話である。
まして、O博士の主張は工法変更まで含めている。こういう考え方は昭和30〜40年代頃に通用したもので、現在の土木ではアナクロと云える。現在の公共事業では、施工での工事費変更は原則として認められない。但し、設計時点と外的条件(用地等制約条件、設計基準等)が変化した場合やコスト圧縮方向への変更は認められる。この結果、事前の地盤調査にはより綿密なものが求められ、それを立案するのは基本的にコンサルタントである。調査不足は設計ミスとされ、それによるコスト増はコンサルタント負担とすることが現代土木の主要な潮流である。
本件では、設計当初想定より岩盤が深いのだから、当然コスト増大方向への変更である。しかも、工法変更まで含まれる。この場合、設計書の組み替え、上位官庁への設計協議、更に竣工後の会計検査等を考えると、設計変更は博士が云うような簡単なものではない。
本件は民間工事であるが、民間企業ほどコスト意識が高いのだから、設計変更は官庁工事以上にシビアになる。設計変更理由として、ボーリングをやっていなかったなどは理由にならない。「始めからボーリングをやっておれば良かったんじゃないか」といわれればそれまでである。
現在の公共工事では、概ね地上高7m以上の構造物、は基礎地盤が、例え岩盤でもボーリングが義務付けられている。岩盤だからといってボーリングを省略し、高い擁壁を構築したところ、竣工後、会計検査院により、岩盤の上からボーリングのやり直しを命令された例はいくらでもある。まして、本件テールアルメは壁高14mに及ぶのだから、例え地すべり地でなくとも、ボーリングを行っておくのは当然である。被控訴人C・D並びにO博士は、永年土木事業に関連してきたのだから、こういうことを知悉しているはずである。要するに、土木の常識を踏まえ、基本に忠実にやるべきことをやっておけば、当鑑定人が本鑑定書(甲60号証)で示した対策工を事前に適用することが出来、何の問題も無い工事だったのである。この点からも、被控訴人らの見解は、現代土木の潮流に著しく逆行するものと云える。
7、まとめ
O博士は同人作成の鑑定書で
(1)100年に1度の大雨の要素が大きい。
(2)横井鑑定で用いた剪断強度は過小である。
(3)再安定計算により横井鑑定より大きい安全率が得られた。
等のことを述べているが、これらは本件事故の本質に何ら関係はない。より重要なことは次の6点である。
なお、次の意見を付け加えて本検討書のまとめとする。
1)被控訴人D、Bは設計図面注意書きの「採石置換」は施工条件であり、控訴人Aはこれに無条件に従うべきと主張する(被控訴人D準備書面10/31付け、被控訴人B準備書面同)。施工条件とは即ち、テールアルメの外的安定に於ける常時1.5、地震時1.2を担保するものである。であれば被控訴人らは、採石置換で上記安全率が得られる根拠を示さなければならない。それが出来なければ採石置換工法は安定性に対する担保能力はなく、設計図に於ける注意書きは単なる「安全弁」と見なされてもやむを得ない。
なお、当鑑定人は理論的根拠の無い単なる注意書きが施工を拘束する、という考え方には極めて強い疑問を感じる。この考え方に従うなら、本来設計段階で解消しておかなくてはならない不確定事項を、何でも注意書きですませばよい、という乱暴で無責任なやり方がまかり通ることになる。全てなにかを条件とするなら、それに対し誰でも理解出来る、正当な根拠を添付することが技術者としての当然の義務と考える。
2)O鑑定による採石置換でも外的安定に関する安全率は1.01にすぎない。被控訴人側は、すべり面強度を過小評価しているとか云っているが、その根拠は極めて薄弱である。従って、これまでのデータによる限り、これを上回る強度が新たに得られる見通しはなく、今後幾ら数字を操作したところで安全率が1.5を満足することは期待されない。
必要安全率1.5を満足出来たのは、崩壊後の対策工事によってのみである。従って、追加対策工事は本体工事とは別工事と見なされるべきである。
3)被控訴人D代理人は、安全率が1.0を僅かでもクリアーすると安定であると主張する。この主張を敷衍すると、第三者にとって、Dの製品は、常に外的安定安全率1.0で設計していると思われてしまう可能性がある。これは将来、㈱Dの製品・企業体質の信用に、重大な誤解を与えかねない。更に、仮に裁判所がこの主張を採用すれば、それは判例として残るので、我が国の土木行政にも影響を与えかねない。例えば、ある不動産業者が宅地開発を計画したところ、盛土の安全率が1.2にしかならなかった。宅地造成規制法では安全率1.5が要求される。当然、行政は当該開発申請を不許可とするか、地盤改良等の行政指導を行う。しかし、業者が大阪高裁判例を持ち出し、安全率が1.0を満足しているといって、指導を拒否したり、訴訟に訴えることもあり得る。結果として技術的曲芸を是認することになり、将来我が国の各所でこの種事故が頻発し、社会的に大きな外部不経済を生むことになる。被控訴人D代理人は、以上の点を十分考慮した上での弁論を展開すべきであろう。 以上